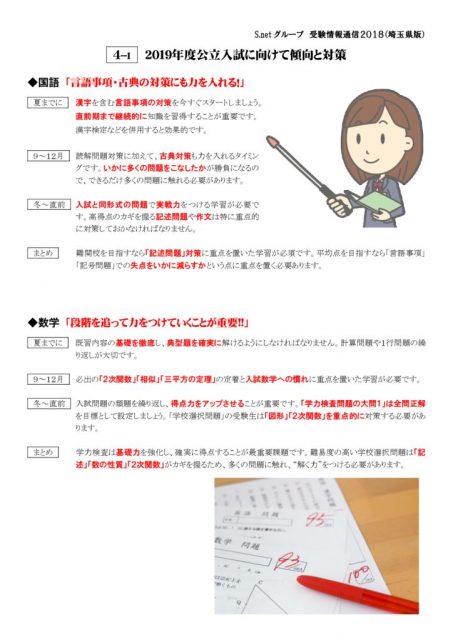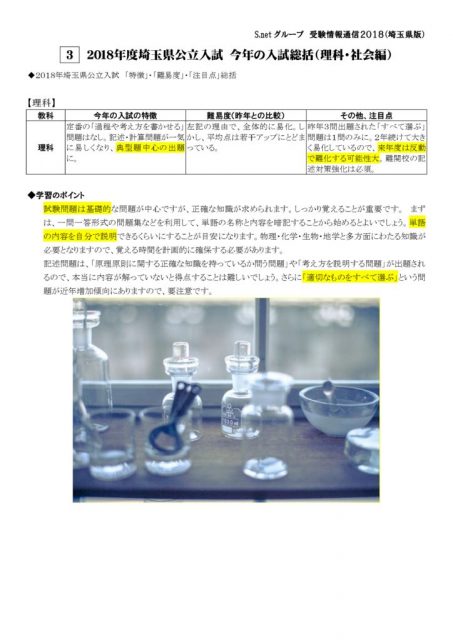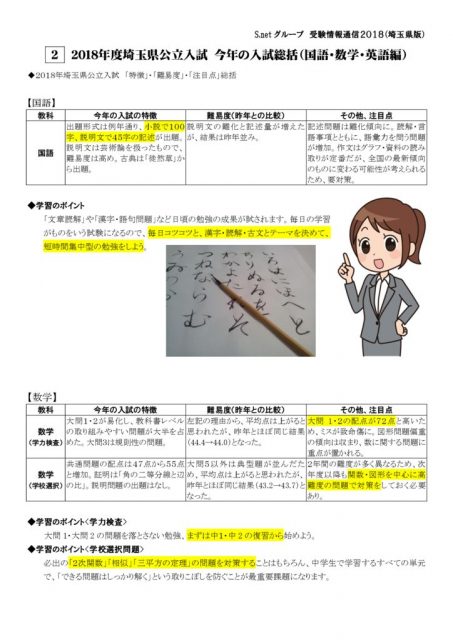埼玉県受験情報 2019年度公立入試に向けて傾向と対策
◆国語 「言語事項・古典の対策にも力を入れる!」
●夏までに
漢字を含む言語事項の対策を今すぐスタートしましょう。直前期まで継続的に知識を習得することが重要です。漢字検定などを併用すると効果的です。
●9~12月
読解問題対策に加えて、古典対策も力を入れるタイミングです。いかに多くの問題をこなしたかが勝負になるので、できるだけ多くの問題に触れる必要があります。
●冬~直前
入試と同形式の問題で実戦力をつける学習が必要です。高得点のカギを握る記述問題や作文は特に重点的に対策しておかなければなりません。
●まとめ
難関校を目指すなら「記述問題」対策に重点を置いた学習が必須です。平均点を目指すなら「言語事項」「記号問題」での失点をいかに減らすかという点に重点を置く必要あります。
◆数学 「段階を追って力をつけていくことが重要!!」
●夏までに
既習内容の基礎を徹底し、典型題を確実に解けるようにしなければなりません。計算問題や1行問題の繰り返しが大切です。
●9~12月
必出の「2次関数」「相似」「三平方の定理」の定着と入試数学への慣れに重点を置いた学習が必要です。
●冬~直前
入試問題の類題を繰り返し、得点力をアップさせることが重要です。「学力検査問題の大問1」は全問正解を目標として設定しましょう。「学校選択問題」の受験生は「図形」「2次関数」を重点的に対策する必要があります。
●まとめ
学力検査は基礎力を強化し、確実に得点することが最重要課題です。難易度の高い学校選択問題は「記述」「数の性質」「2次関数」がカギを握るため、多くの問題に触れ、“解く力”をつける必要があります。
◆英語 「文法力・語彙力をつけ、“書く力”を養う!!」
●夏までに
基本的文法と単語の習得が最重要課題です。短めの文章で単語補充、内容把握、英問英答などの設問に慣れて、英文読解の対策もスタートさせる必要があります。
●9~12月
“書く”ことに重点を置いた入試対策を行うタイミングです。「学校選択問題」の受験生は“読解力”の養成もこの時期に行わなければなりません。他県入試にも積極的にチャレンジし、実力養成をはかりましょう。
●冬~直前
入試と同形式の問題で入試の英語に慣れることが必要です。「学校選択問題」の受験生は「長文読解」と「英作文」に重点を置いた対策が欠かせません。
●まとめ
文法力、語彙力がカギを握るのが入試です。「空所補充」「英作文」などの記述問題が得点で差をつけるキメテとなります。学校選択問題の長文読解、記述対策、作文対策には他県入試を利用しましょう。
(作成情報協力:株式会社エデュケーショナルネットワーク)