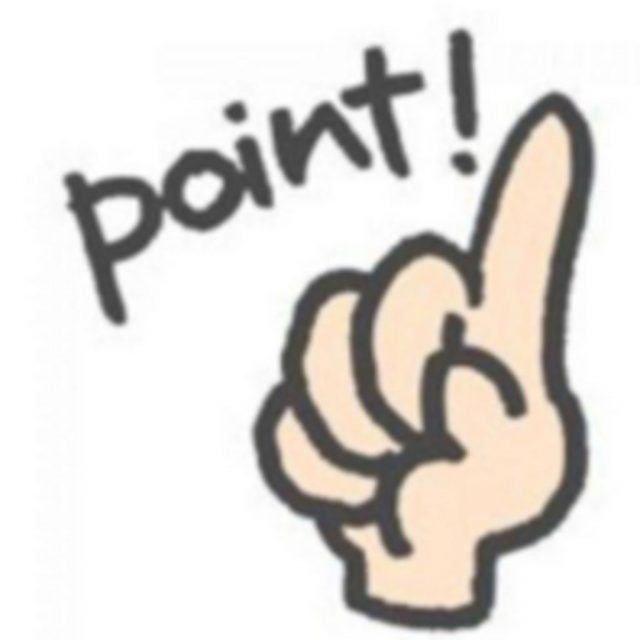国立大学入試の基本方針が発表されました。
「平成32年度以降の国立大学の入学者選抜制度―国立大学協会の基本方針―」の公表及び
「平成32年度以降の国立大学の入学者選抜制度―国立大学協会の基本方針―」の策定に当たって
(会長談話)の発表について。
↓↓↓↓↓
http://www.janu.jp/news/teigen/20171110-wnew-nyushi.html
ポイントを抜粋しますと…
(1)5教科7科目の原則
平成32年度以降の「大学入学共通テスト」(以下、「新テスト」)導入後も
これまでの方針を踏襲しすべての国立大学は
「一般選抜」においては第一 次試験として
高等学校等における基礎的教科・科目についての学習の達成度を測るため
原則5教科7科目を課す。
(2)英語
新テストの枠組みにおける5教科7科目の位置づけとして
認定試験を「一般選抜」 の全受験生に課すとともに
平成35年度までは
センターの新テストにおいて 実施される英語試験を併せて課すこととし
それらの結果を入学者選抜に活用する。
(3)記述式問題
新テストの5教科7科目を課す原則の下
記述式問題を含む国語及び数学 を「一般選抜」の全受験生に課す。
①一般選抜
すべての受験生に
個別試験で論理的思考力・判断力・表現力を評価する
高度な記述式試験を課すこととする。
教科・科目を含め
その具体的な内容・方法については各大学・学部の主体的な判断に委ねられるが
各大学・学部が
募集要項等において出題意図、求め る能力等を明確にした上で
受験生に課す。
(i)調査書や志願者本人が記載する資料等の活用
調査書や志願者本人が記載する資料、面接等を活用する方法を検討し
実施可能なものから順次導入していく。
また、併せて
各大学・学部は
調査書等をどのように活用するのかについて募集要項等に明記する。
②「総合型選抜」 ・「学校推薦型選抜」
一定の学力を 担保した上で
調査書等の出願書類に加えて
小論文や面接、プレゼンテーション など多様な評価方法を活用し
これら学力試験以外の要素を加味した
「総合型選抜」・「学校推薦型選抜」などの
丁寧な入学者選抜の取組みを加速・拡大する。
くわしい内容は以下からご確認ください。
↓↓↓↓↓
http://www.janu.jp/news/teigen/20171110-wnew-nyushi.html